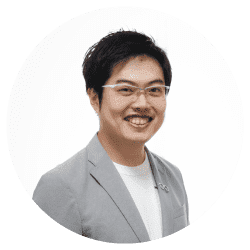- “採用・定着”マニュアル
【介護事業所の職員が辞める理由とは?】人材不足の現状と離職を防ぐ改善策について解説
2025/2/28
2025/03/03

介護業界では慢性的な人手不足が問題となっており、多くの事業所が職員の確保に苦労しています。特に、採用してもすぐに辞めてしまうケースが多く、結果的に残った職員の負担が増え、さらに離職者が増えるという悪循環が生じています。
厚生労働省の調査によると、介護職員の離職率は他業種と比べても高く、特に中小規模の事業所では人材の定着が大きな課題となっています。離職が続くと、利用者へのサービスの質が低下し、事業所の経営にも悪影響を及ぼします。
本記事では、介護事業所の職員が辞める主な理由を解説し、離職を防ぐための具体的な対策を紹介します。
Contents
介護事業所の職員が辞める主な理由
介護事業所の職員が辞めてしまう主な理由は、給与や労働条件と業務内容の不釣り合いや人間関係のトラブルです。
給与・待遇が見合わない(低賃金・昇給が少ない)
介護職員の離職理由として最も多いのが「給与の低さ」です。介護業界は社会的に重要な役割を担っているにもかかわらず、他の業種と比べて賃金が低い傾向にあります。特に、資格や経験に応じた昇給が少ないことが不満となり、より条件の良い職場を求めて転職するケースが後を絶ちません。
また、夜勤手当や特別手当があっても基本給が低いため、生活の安定が難しいと感じる職員も多いのが現状です。
仕事の負担が大きい(身体的・精神的負担)
介護職は身体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。入浴や移乗介助などの業務では腰を痛めることが多く、慢性的な疲労を抱える職員も少なくありません。
また、認知症の利用者の対応や、家族とのコミュニケーションなど、精神的なストレスを感じる場面も多くあります。さらに、人手不足により一人あたりの業務量が増え、疲労やストレスが限界に達し、退職を選ぶ職員もいます。
人間関係のトラブル(職場のいじめ・パワハラ)
介護業界では、職場の人間関係が原因で辞めるケースも多く見られます。特に、指導者の厳しい態度や、職場内の派閥争い、いじめが問題になることがあります。新人職員が先輩職員から適切な指導を受けられず、孤立してしまうことも少なくありません。
また、利用者やその家族とのトラブルが発生しやすく、現場での対応に苦労することもストレスの一因となります。人間関係の悪化は職員のモチベーションを低下させ、退職を決意する大きな要因になります。
労働環境の問題(シフトの不安定さ・長時間労働)
シフトの不安定さや長時間労働も、離職につながる要因の一つです。介護業界では、早番・遅番・夜勤があるため、生活リズムが不規則になりやすく、心身に負担がかかります。特に、人手不足の職場では休みが取りにくく、休日でも急な呼び出しがあるケースもあります。
また、有給休暇を取得しにくい環境も多く、ワークライフバランスを保つことが難しいと感じる職員が増えています。
キャリアアップの機会が少ない(昇進・資格取得支援の不足)
介護職は資格によってキャリアアップが可能な業界ですが、事業所によっては十分な教育制度が整っておらず、職員がスキルアップできる環境がないことがあります。資格取得の支援制度がなかったり、昇進の機会が限られていたりするため、将来に希望を持てずに辞めてしまうケースもあります。
特に、モチベーションの高い職員ほど、キャリアアップが見込めない職場では働き続ける意義を感じられず、より良い環境を求めて転職を考える傾向があります。
介護職員の離職を防ぐための改善策
介護事業所の職員の早期離職防止策としては給与等の労働条件の改善や人間関係の改善などの労働環境全体に関することやキャリアアップ制度の確立等の人材育成に関する制度構築が重要なポイントです。
給与・待遇の見直し(賃金体系の改善・助成金の活用)
介護職員の給与を適正な水準に引き上げることは、離職防止において最も重要な対策の一つです。まず、基本給の見直しや昇給制度の整備を行い、職員が長く働ける環境を作ることが求められます。
さらに、夜勤手当や資格手当を充実させることで、職員のモチベーション向上につながります。
また、介護職員の処遇改善を目的とした「介護職員処遇改善加算」などの助成制度を活用することで、賃金向上が可能です。これらの制度を適切に利用し、職員へ還元することで、給与面での不満を軽減できます。
働きやすい労働環境の整備(シフト調整・残業管理)
介護職はシフト勤務が基本ですが、過重労働が続くと職員の負担が増え、離職の原因になります。そのため、適切な人員配置を行い、職員一人ひとりの負担を軽減することが重要です。
特に、シフトの事前調整を徹底し、希望休や連休を取りやすくすることで、ワークライフバランスを向上させることができます。
また、残業時間の管理を徹底し、労働時間が長くなりすぎないようにすることも重要です。ICTを活用して業務の効率化を図り、記録業務の簡素化や、業務分担の見直しを進めることで、無駄な残業を減らすことができます。
人間関係の改善(ハラスメント防止・チームワーク強化)
職場の人間関係が良好であることは、職員の定着率を高める上で不可欠です。まず、パワハラ・セクハラを防ぐための対策を徹底し、問題が発生した際には迅速に対応できる相談窓口を設置することが望まれます。
また、定期的なアンケート調査を実施し、職場環境の課題を早期に発見することも有効です。
さらに、職員同士のチームワークを強化するための取り組みも重要です。例えば、定期的なミーティングや、研修・勉強会を開催することで、職員同士が意見を交換しやすい環境を整えることができます。また、レクリエーションや懇親会を通じて、職員間の信頼関係を深めることも、働きやすい職場づくりにつながります。
キャリア支援の充実(研修制度・資格取得支援)
介護職員が長く働き続けるためには、キャリアアップの道を明確に示すことが重要です。まず、研修制度を充実させ、新人職員だけでなく、経験者向けのスキルアップ研修を提供することが効果的です。これにより、職員が成長を実感しながら働ける環境が整います。
また、資格取得支援制度を導入し、介護福祉士やケアマネージャーなどの資格取得に向けた費用補助や学習支援を行うことも、職員のモチベーション向上につながります。特に、キャリアアップの明確なビジョンを示すことで、「この職場で長く働きたい」と思える環境を作ることができます。
実践的な対策
介護職員の離職を防ぐためには、労務管理の観点から適切な制度を整備することが重要です。まず、給与体系の見直しとして、職員のスキルや経験に応じた昇給制度を明確にし、「介護職員処遇改善加算」などの助成制度を最大限に活用することが有効です。これにより、賃金の向上が可能となり、職員の満足度を高められます。
また、労働時間の適正管理も重要な課題です。長時間労働を防ぐために、勤怠管理システムを導入し、業務の偏りをなくすことで、ワークライフバランスを改善できます。さらに、定期的な労務監査を実施し、過重労働や有給取得率をチェックすることで、働きやすい環境を維持できます。
人間関係のトラブル防止策としては、ハラスメント防止規程を整備し、相談窓口を設置することが有効です。また、職員のキャリアアップ支援として、資格取得補助制度の導入や、研修制度の充実を図ることも重要です。
まとめ
介護事業所の職員が辞める主な理由として、給与・待遇の不満、仕事の負担の大きさ、人間関係のトラブル、労働環境の問題、キャリアアップの機会の不足が挙げられます。これらの課題を放置すると、職員の離職が続き、事業所の運営や利用者へのサービスにも悪影響を及ぼします。
離職を防ぐためには、給与体系の見直しや助成金の活用、働きやすいシフト制度の導入、人間関係の改善、キャリア支援の充実など、多方面からの対策が必要です。特に、社会保険労務士の視点から、労働環境の整備やハラスメント防止策、労働時間の適正管理を行うことが、職員の定着率向上につながります。
介護業界の人材不足が深刻化する中で、職員が長く働きたいと思える環境を整えることが事業所の成長に不可欠です。社会保険労務士などの外部の専門家とも連携しながら、働きやすい職場づくりを進めることで、職員のモチベーション向上と離職防止を実現できます。