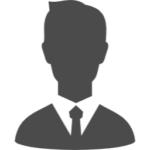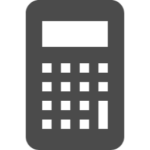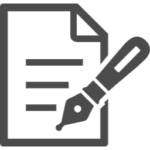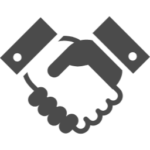【採用内定の取り消し】妊娠・出産を理由とする内定取り消しは有効か
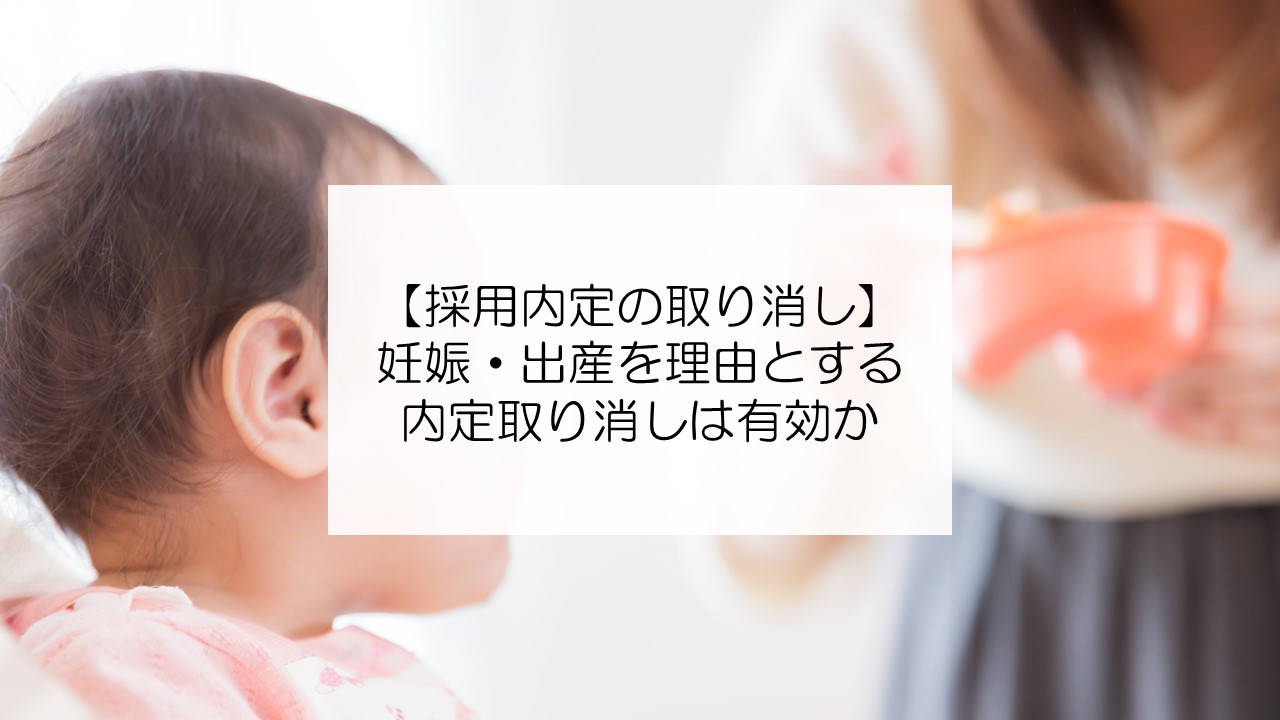
採用内定後に内定者の妊娠・出産が判明した場合、業務への支障や人事・人材育成計画への影響を考慮し、できれば内定を取り消したいと考える企業が少なくないようです。
今回は、妊娠・出産を理由とする内定取り消しの法的な有効性について解説し、内定者の妊娠・出産が判明した場合に企業がとるべき対応を検討します。
┃採用内定と内定取り消し
○採用内定は労働契約成立を意味する
採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約」と言われ、既に労働契約が成立していると考えられています。一般的な採用活動の流れでは、内定者が内定通知書を受け取った段階で労働契約が成立したと考えられます。そのため、採用内定後に妊娠が発覚した場合、妊娠を理由とした内定取り消しは解雇と同様に扱われることになるため、認められないと考えられます。
新卒採用や中途採用では、求職者に内定通知書が送られ、内定者がそれに応じて内定承諾書(誓約書)を提出することで採用内定が社内で確定し、入社日に入社手続きを行うことで内定者はその会社に所属することになります。
内定通知書・承諾書の取り交わし以外に、労働契約書の締結など、労働契約を結ぶための特別な手続きは行われません。内定者は内定通知によって採用が決まったと判断し、就職活動を停止します。
社員募集に応募した段階で応募者は労働契約締結の意思を示しており、求人者側である会社は、採用選考の後、内定通知によってそれに応じる意思を示しているため、内定通知によって労働契約が成立することになります。
○採用内定を取り消すことは解雇に当たる
採用内定によって労働契約はすでに成立しているため、内定取り消しは会社側からの一方的な労働契約解除、つまり解雇に当たります。
『事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(いわゆる「マタハラ指針」)』でも、妊娠したことを理由とした解雇その他不利益な取扱いを示唆するものは認められない典型例として明示されています。
○内定取り消しが認められる要件
会社都合の内定取り消しは、原則として認められません。内定取り消し(=解雇)が有効と認められるためには、解雇を行う「合理的な理由」があり、「社会通念上相当」であると見なされない限り、不当解雇(解雇権の濫用)となります。
内定取り消しをする場合、以下のような条件に当てはまれば正当とみなされる可能性があります。
- ・内定者が卒業予定の大学を卒業できなかった場合
- ・内定通知書・承諾書で定めた必要資格を取得できなかった場合
- ・病気・障害により内定者が長期にわたって就業できない場合
- ・履歴書の内容に重大な虚偽があった場合(学歴・資格の詐称など)
- ・刑事事件で有罪判決を受けた場合
- ・整理解雇が必要になり、内定者を減らさざるを得なくなった場合
以上のような内定取り消し事由については、内定通知書であらかじめ明示しておくと良いでしょう。
○内々定は原則として自由に取り消せる
内定通知が出されていない「内々定」の段階であれば、労働契約が成立していないため、取り消しても解雇とはならず、原則として自由に取り消すことができると考えられます。
ただし、妊娠・出産を理由として不採用にしたとみなされれば、男女雇用機会均等法違反となるなどトラブルに発展する恐れもあります。
┃妊娠・出産を理由とする内定取り消し
○妊娠・出産を理由とする内定取り消しは法律違反
妊娠・出産を理由とする内定取り消し(=解雇)は、男女雇用機会均等法で禁止されています。男女雇用機会均等法では、解雇だけではなく妊娠・出産を契機として不利益取り扱いをすることも同時に禁止しています。
妊娠・出産を契機として不利益取り扱いとは、解雇・内定取り消しの他、降格、減給、不利益な人事考課・配置転換などがあります。
男女雇用機会均等法
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
○妊娠・出産・育休等を契機とした不利益取り扱いは違法
『妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A』では、妊娠・出産・育休等を契機とした不利益取り扱いは違法とされています。ここでいう「契機として」というのは具体的には、「原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合」とされています。
人事労務管理上の理由で配置転換や異動をする場合でも対象社員とよく話し合い、不利益取り扱いとならないよう十分な配慮が必要になるでしょう。
○選考過程で妊娠・出産を理由として応募者を不利に扱うのも違法
内定取り消しが難しいなら採用選考の段階で妊娠・出産を理由に応募者を選別すればよいと考える会社もあるかもしれませんが、採用試験・面接・選考などの過程において男女で異なる扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁じられています。
妊娠・出産に関して言えば、次のような言動が男女雇用機会均等法違反となります。
- ・面接時に、女性に対し「妊娠しているかどうか」「妊娠・出産する予定があるか」を質問する(男性に対しては成り立たない質問なので、男女で異なる扱いをすることになる)
- ・面接時に、将来子どもが生まれた場合に就業を継続する意思があるかどうか、女性にだけ質問する(質問は両方の性に対してするが、女性の回答のみ採用・不採用の判断要素とする)
- ・「体力の程度」や「転居を伴う転勤への対応力」を選考基準として設定する(その基準が実際の業務内容や事業計画とかけ離れていて不合理な場合)
- ・こうした対応をもとに、実際に妊娠・出産を理由として女性応募者を不採用とする
○妊娠・出産を理由とする内定取り消しが例外的に認められるケース
『妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A』では、妊娠・出産・育児休業等を契機としていても、法違反ではないとされる例外を示しています。それが、『業務上の必要性から不利益取扱いをせざるを得ず、業務上の必要性が、当該不利益取扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき』と『労働者が同意している場合で、有利な影響が不利な影響の内容・程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、一般的な労働者なら同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき』です。
これらは、相当ハードルが高く認められるとすれば倒産寸前の状態で他に取り得る手段がない(やり尽くした)状態だったり、本人と十分な話し合いが行われ納得のいく待遇を用意していたりする場合だけだと考えます。

┃整理解雇と内定取り消し
○妊娠・出産等を理由とする整理解雇者の人選
求職者に内定を出した後に業績悪化などで整理解雇が必要になった場合でも、妊娠・出産を理由に特定の内定者を不利益に扱うことは法律違反になり得ます。整理解雇を行う場合、「1.人員整理の必要性」「2.解雇回避努力義務の履行」「3.被解雇者選定の合理性」「4.解雇手続の妥当性」の4つの要素から妥当性が判断されます。妊娠をしているから、出産・育休等で労働能率が落ちているからといった理由では、被解雇者の選定要件としては不十分であると考えることができます。
○やむを得ないときは早めに誠実な対応をすること
原則として、妊娠・出産を理由とする内定取り消し(解雇)はできませんが、入社前に退職勧奨を行って退職してもらう(入社辞退してもらう)という選択肢は考えられます。
急激な経営悪化など入社後に任せる予定だった仕事がなくなってしまったり、入社後に任せられる業務が力仕事や危険業務になってしまったりするなど、妊娠・出産により就労がとりわけ困難になる業種・職種の場合には、採用内定者本人の健康のことも考え入社を辞退してもらうこともやむを得ないとみなされる余地があるでしょう。
ただし、採用選考や採用内定のときとは別の職種を提案する場合などは、内定者本人にとっては不利益取り扱いとなることも考えられるため丁寧で誠実な対応が求められます。
┃妊娠・出産への会社の姿勢は採用や人材定着に影響する
ここでは、妊娠・出産と採用内定者をテーマとして取り上げましたが会社の姿勢はその後の採用活動や人材定着にも影響を及ぼすことを認識する必要があります。いわゆる両立支援に消極的な会社というイメージを持たれると会社にとっては悪影響となる恐れがあります。
また、こうした問題が原因でトラブルになり会社名が報道されるような事態になれば、信用に大きく傷がつくことを自覚するべきでしょう。
┃妊娠・出産・育休等に関する制度
・産前産後休業(労働基準法)
産前産後休業は、労働基準法第65条に定められた労働者の権利であり、労働者からの請求があった場合には、認める必要があります。
・出産手当金、出産育児一時金(健康保険法)
健康保険から給付される出産手当金と出産育児一時金については、健康保険の被保険者であれば、入社直後でも受給することは可能です。
・育児休業(育児介護休業法)
最長で2歳まで、本人の希望により育児休業を取得することが可能です。ただし、労使協定により「入社1年未満の社員からの育児休業の申し出を拒むことができる」旨の規定があれば、申し出を拒むことができます。
・育児休業給付金(雇用保険法)
育児休業給付の受給資格は原則として、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12箇月以上あることが必要です。この要件を満たしていれば育児休業給付金の受給対象となります。
┃まとめ
今回は、妊娠・出産を理由とする内定取り消しの法的な有効性について解説し、内定者の妊娠・出産が判明した場合に企業がとるべき対応についてお伝えしてきました。
妊娠・出産は本来であればおめでたいことである一方、代わりの人を探したり、他の人に業務を受け持ってもらったり等の調整も必要になるため、中小企業にとっては大きな負担になることも事実です。
会社としては、国の制度も最大限活用しつつ、丁寧で誠実な対応が求められます。
*厚生労働省
「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(いわゆる「マタハラ指針」)」