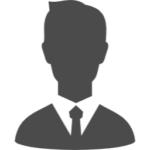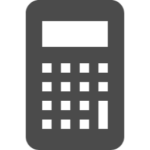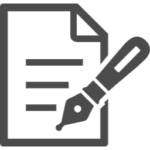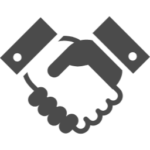【賃金控除の有効性】会社の貸与品を毀損したとき賃金から弁償させることはできるか
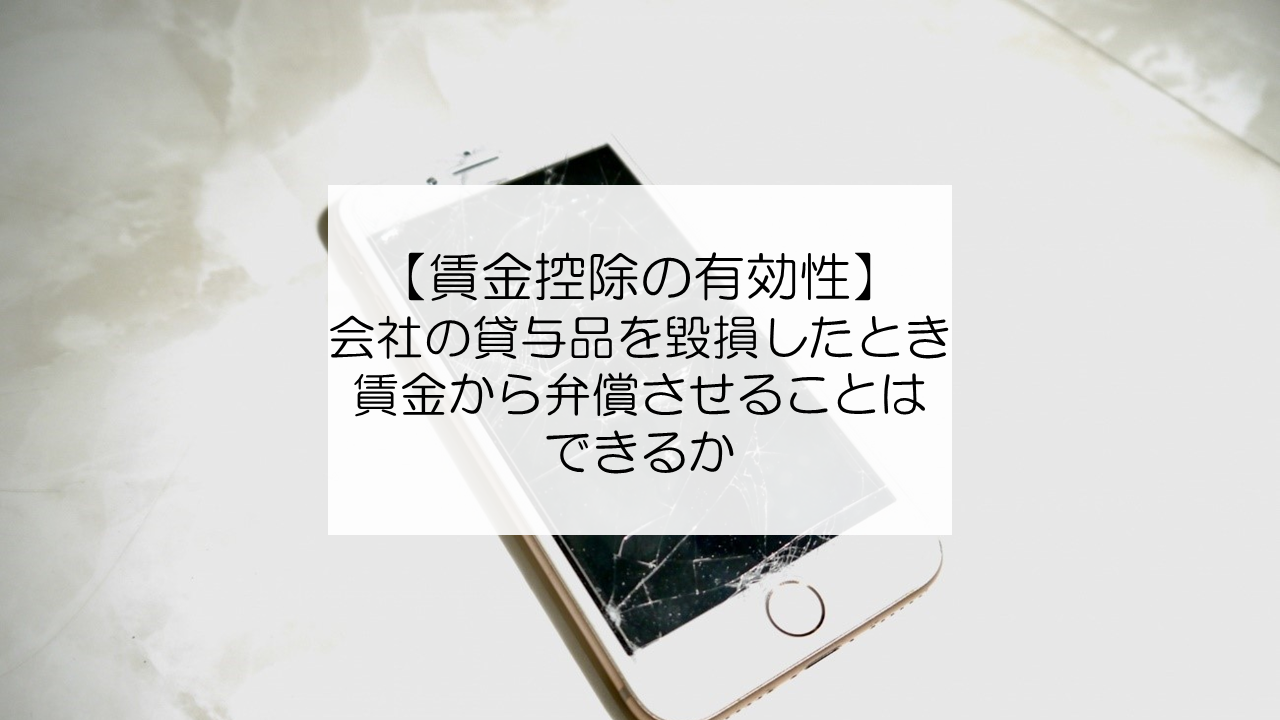
会社が社員に対してパソコンや携帯電話などの貸与品を与えるのは、多くの会社で行われています。そのとき、社員が会社の貸与品を毀損・紛失した場合、会社は、社員の賃金から弁償額を控除できるのかという問題があります。
今回は、社員が会社の貸与品を毀損・損失した場合に社員が弁償する義務があるのか、弁償をしなければならないとなったときに賃金から弁償額を控除できるかどうかについて解説します。
┃社員は貸与品の毀損・紛失について弁償する義務を負うか
〇社員に過失がある場合は損害賠償責任を負う
社員は、会社との労働契約契約において、会社に損害を与えないよう注意する義務を負っていると考えられます。そのため、社員の故意または過失によって貸与品を毀損・紛失した場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことになるでしょう。
一方、貸与品の毀損・紛失について、社員が十分に注意していて過失が認められない場合や、過失の程度が軽い場合には、社員は損害賠償責任が発生しない場合もあります。
以上をまとめると、会社が社員に貸与品の弁償を求めることができるのは、貸与品の毀損・紛失について社員に過失がある場合のみと考えることができます。
会社に損害が発生した場合にその実費弁償額の範囲内で弁償させることは問題ありませんが、就業規則であらかじめ「■■を紛失または破損した場合は○○円を控除する」ということを定めておくことはできないので注意が必要です。
〇社員が弁償の義務を負う場合でも原則として全額は負担させられない
社員が弁償の義務を負う場合でも、全額の弁償義務を負うわけではありません。
例えば社員がパソコンやスマートフォンを紛失したとしても、それらの新品相当の金額を弁償させることは合理的ではありません。なぜかというと、パソコンやスマートフォンも使用している年数によって価値が減っていると考えられるからです。
さらに使用者責任の問題もあります。社員が会社の業務に関して会社に損害を与えた場合、社員は会社のために行動していたのであって、社員に全責任を負わせるのは不公平と言えます。そのため、社員が弁償の義務を負う場合でも、その負担割合は損害額の一部に制限されます。
裁判事例では、会社と社員の立場を考慮し、社員の負担割合を4分の1程度にとどめるケースが多いです。
つまり、社員が会社の貸与品について弁償の義務を負う場合でも、その金額は、中古品の額を基準として、その4分の1程度が限度と考えることができます。
たとえば、社員が新品価格20万円、中古価格(時価)10万円のパソコンを毀損した場合、会社が社員に弁償させられるのは、2万5,000円程度です(10万円×4分の1)。
なお、社員が会社の貸与品を盗んだり、故意に毀損したりした場合には、会社が損害を負担するのは不公平なので、社員が全額の弁償義務を負います。
茨城石炭商事事件(1976年7月8日/最高裁判所第一小法廷/判決)
石油等輸送会社Yに雇用された従業員Xが、重油を満載したタンクローリーの運転を臨時的に命じられ、渋滞し始めた国道を走行中、急停止した先行車両に追突した。Yは損害賠償金約40万円を相手に支払う一方、Xにその全額を賠償するよう提訴した。Xの仕事の内容、勤務態度や給与、事故の態様、Xの過失の内容などからして、YがXに請求できるのは、信義則上、損害額の4分の1が妥当であるとした。

┃会社は社員の賃金から弁償代を控除できるか
〇貸与品を毀損・紛失した場合の罰金額を予定することはできない
会社は、社員に貸与品を与える際に、「毀損・紛失した場合は〇〇円の罰金を支払う」などの契約を交わすことはできません。
労働基準法では、会社と社員との間で、社員が労働契約の不履行について違約金や一定の損害賠償を支払う内容の契約を交わすことを禁止しています(労働基準法第16条)。
そのため、社員による貸与品の毀損・紛失について、会社が予め決められた額の罰金を科すことは労働基準法第16条に違反するため許されません。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
〇弁償金の請求と懲戒処分
懲戒処分における減給制裁は、「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とされています(労働基準法第91条)。損害に対する弁償と懲戒処分による減給制裁は分けて考えるべきでしょう。
なお、懲戒処分として減給制裁を科す場合には、あらかじめ就業規則に規定が定められている必要があります。
〇社員の同意なく賃金から弁償金を控除することはできない
労働基準法第24条第1項は、労働者の賃金について、全額を直接支払わなければならないと規定しています。そのため、会社が社員に対して弁償金を請求できる場合でも、会社が一方的に弁償代と社員の賃金を相殺することは許されません。
そのため、会社が社員に対して弁償を求める場合には、決まった賃金はその通り支払った上で会社と社員の合意によって弁償金を支払ってもらうことになります。
以上をまとめると、会社が社員の同意なく一方的に賃金から弁償代を控除することは許されませんが、会社と社員が合意した場合には、賃金から弁償金を控除できます。
なお、会社と社員との合意による賃金の控除が認められるのは、社員が自由な意思に基づいて合意したと言える場合のみです。なぜなら、社員が会社の圧力で合意せざるを得なかったような場合には、賃金全額支払いを定めた労働基準法第24条の脱法行為になってしまうからです。
会社としては、社員の賃金を控除する際には合意書を作成するなどして、社員が自分の意思で控除に応じたことの証拠を残しておくようにしましょう。
〇労使協定を締結していれば賃金から弁償代を控除することも許される
労働基準法第24条1項はただし書きにおいて、労使協定がある場合には賃金の一部を控除することを認めています。
そのため、賃金から弁償金(損害賠償額)を控除することを認める労使協定を締結していれば、賃金から弁償代を控除することも可能です。
┃まとめ
貸与品の弁償金を賃金から控除できるかについては、次の順番で検討する必要があります。
- ・そもそも社員が弁償の義務を負うのか
- ・弁償の義務を負うとして金額はいくらか
- ・その額を賃金から控除できるか
社員が弁償の義務を負う場合でも、賃金から弁償金を控除するには、社員との合意もしくは労使協定の締結が必要です。さらに、会社が負った損害相当額の弁償を求めたり、懲戒処分を行ったりするためには就業規則の規定も必要です。
会社としては不測の事態に備えて、就業規則や労使協定の整備、社員に過度な負担を掛けないための損害保険への加入などの対策を取っておくことが求められます。
※2023年8月28日、内容を更新しました。