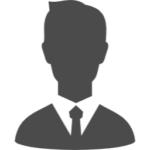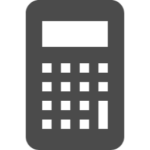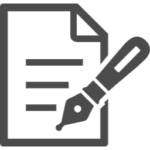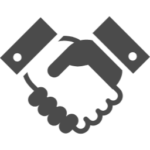退職における就業規則の効力
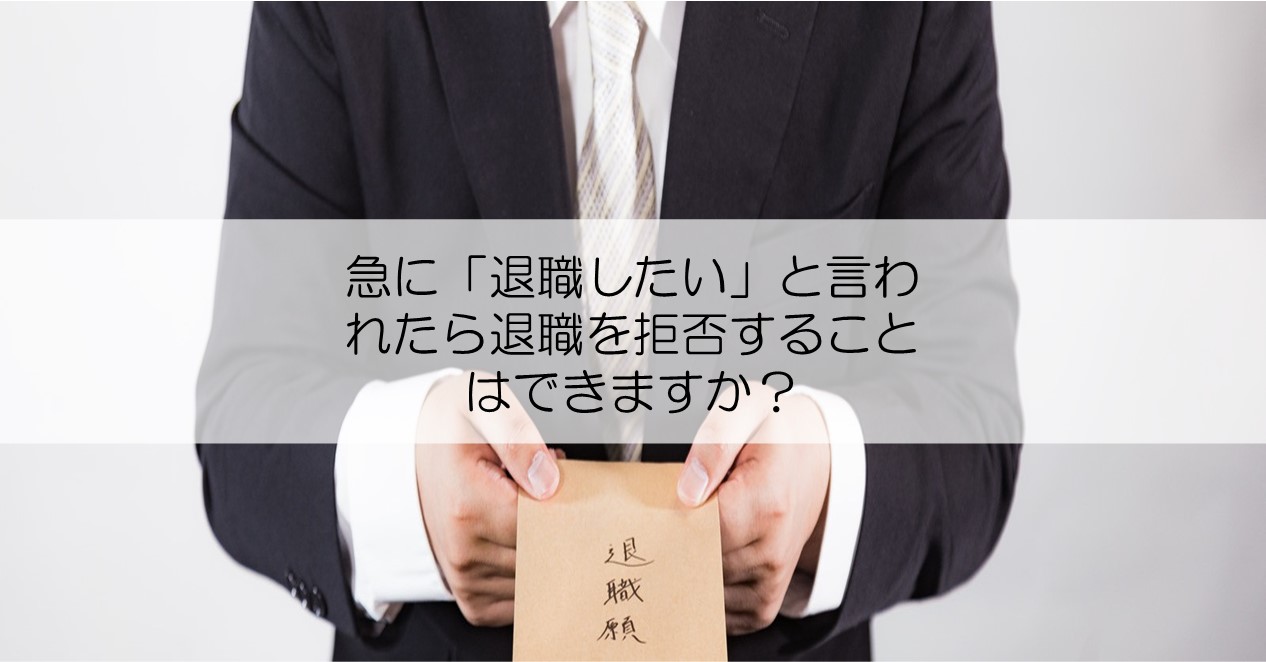
従業員の退職は、企業における最重要事項です。企業と従業員が合意のうえで退職する場合は問題ありませんが、意見の相違やトラブルが生じると、大きな問題に発展してしまいます。
退職トラブルを防ぐためにも、就業規則や雇用契約書に退職に関するルールをしっかり定めておくことが大切です。
一方で「民法上、退職の2週間前に申し出れば退職できる」といった話を耳にしたことがあるかもしれません。
では、会社側が「退職の1ヶ月前までに申し出ること」と就業規則で定めている場合、このようなルールと法律の関係はどうなるのでしょうか。
特に、近年は退職代行の知名度の高まりとともに退職における就業規則の効力について注目されています。
当社にも「就業規則に記載しているのに、直前になって退職の申し出がされる」「就業規則違反について処分はできないのか」等の相談を多くいただきます。
今回は、社会保険労務士法人GOALが退職と就業規則について解説していきます。ぜひ、最後までご覧ください。
法的な退職の意思表示と就業規則の関係
従業員から「○月○日をもって退職したい」と意思表示(申し出)があった場合、「労働契約を解約したい」と申し出があったことになります。つまり、法的な退職の意思表示です。
会社がこの申し出を承諾したとき、労働契約の解約が成立します。基本的にはその後に従業員からの一方的な撤回(取り消し)はできないと考えられています。
民法では、退職の意思表示については下記のとおり規定されています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法によると、無期雇用の従業員は2週間前に退職の申し入れをすれば、2週間経過後に雇用関係が終了するとされています。
一方で、多くの企業では退職をする際には「1ヵ月以内に会社に申し出なければならない」と規定しているケースが多くあります。
会社内のルールである就業規則と民法のどちらが優先されるかは議論が分かれるところです。
民法の規定が適用されると考える場合、期間の定めのない労働契約(正規雇用)においては、いつでも労働契約の解約を申し入れることができます。
さらに、退職願を提出する等、退職の意思表示をした日から2週間を経過すると自動的に労働契約が終了します。
ただし、民法627条では、労働者側の権利が規定されています。事業主側から労働契約の解約(解雇等)を申し出る場合には、労働基準法が適用されるので注意が必要です。
また、正規雇用労働者が月給で賃金が定められている場合には、民法第627条第2項の規定にも注意が必要です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条2項
第六百二十七条の二 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
民法627条2項の規定では、退職の申し入れは、賃金計算期間の前半に次期以降についてすることとされています。
例えば、下記のケースでは、1月15日までに退職の意思表示をする必要があります。
- 賃金計算期間:1日~末日
- 退職希望日:2月末日
- 退職の意思表示:1月15日まで
退職のルールと就業規則
就業規則で退職のルールを定める場合、次のようなルールが規定されていることが一般的です。
先の就業規則と民法の優先順位を考えると、就業規則に2箇月や3箇月としても実際には、その規定の役目を果たしていないことの方が多いです。
就業規則違反で処分することはできるか
「1箇月前に申し出ること」とあるのに直前になって退職の申し出をしたことに対して就業規則違反での処分は、事実上できないと考えられます。
懲戒処分をするとしても「けん責(注意・指導)」程度が妥当だと考えられるので、これから退職する人に対しては、あまり効果はないと言えます。
当然のことながら「就業規則違反だから退職を認めない」ということもできません。
退職の意思表示を撤回できる場合
従業員が退職の意思表示を撤回できる場合もあります。具体的に見ていきましょう。
勘違いやまちがいで退職の意思表示をした場合
業務上のミスをした場合、実際は懲戒事由ではないのに「このままだと懲戒解雇になるから自主退職した方がいい」などと言われてそれを信じて退職届を提出したようなケースがこれにあたります。
当該ミスが実際に懲戒解雇事由にあたらないのであれば、そもそも退職をする理由がないので退職届の提出自体が間違いということになります。
この場合には、民法第95条に基づき退職の意思表示を取り消すことができます。
騙されたり脅迫されたりした場合
人員整理をしたい場合などに過去の処分歴を持ち出して「自分から退職届を出さないと損害賠償もあり得る」などと持ち掛けるようなケースです。
この場合にも、民法第96条に戻付き退職の意思表示を取り消すことができます。
退職の意思表示を撤回させないために
社労士法人GOALで実際に取り扱った事例を見てみると退職の意思表示を撤回するような従業員は、在籍中になにかしらの問題(労務トラブル)を抱えているケースが少なくありません。
この場合、会社としては退職の意思表示を尊重して、「自己都合による退職」で処理したいという考えもあります。
そのため、「退職届を受け取った」「退職の意思表示を受理した」旨をメール・チャット・書面で明確に示しておくことが重要です。
会社の意思はしっかりと示した上で、会社に残って欲しい人なのであれば特別に撤回に応じるということも可能です。
退職と就業規則に関するよくある質問
最後に、退職と就業規則に関するよくある質問をご紹介します。
- 就業規則に退職を認めないと規定できますか?
就業規則に「退職を認めない」との規定は認められません。
就業規則や民法、労働基準法等、すべてのルールに優先して憲法第22条で職業選択の自由が定めれています。この憲法の大原則により、退職の自由は保障されています。そのため退職は労働者の権利として保護されています。
事業主としては、退職時のトラブルを防いだり引き継ぎを円滑にしたりするためにも日々の接し方が重要です。
たとえ従業員が退職を決意したとしても最後は気持ちよく送り出せることがお互いにとってベストといえるでしょう。
- 就業規則に反したことをもって退職届の受理を拒否できる?
民法627条の解約の申し入れに基づく、退職届の受理を拒否することは難しいと考えていいでしょう。
正当な権利である退職届を拒否すると、慰謝料請求や労働基準監督署への通報に繋がる可能性があります。したがって、退職届を受理した上で協議をすることが重要です。