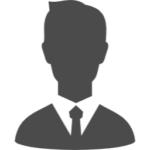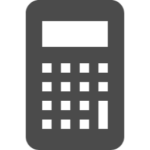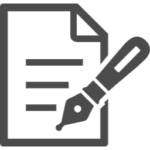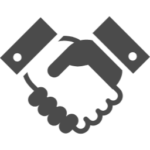【労災保険の特別加入】中小企業事業主のための業務災害・通勤災害対策の基礎知識
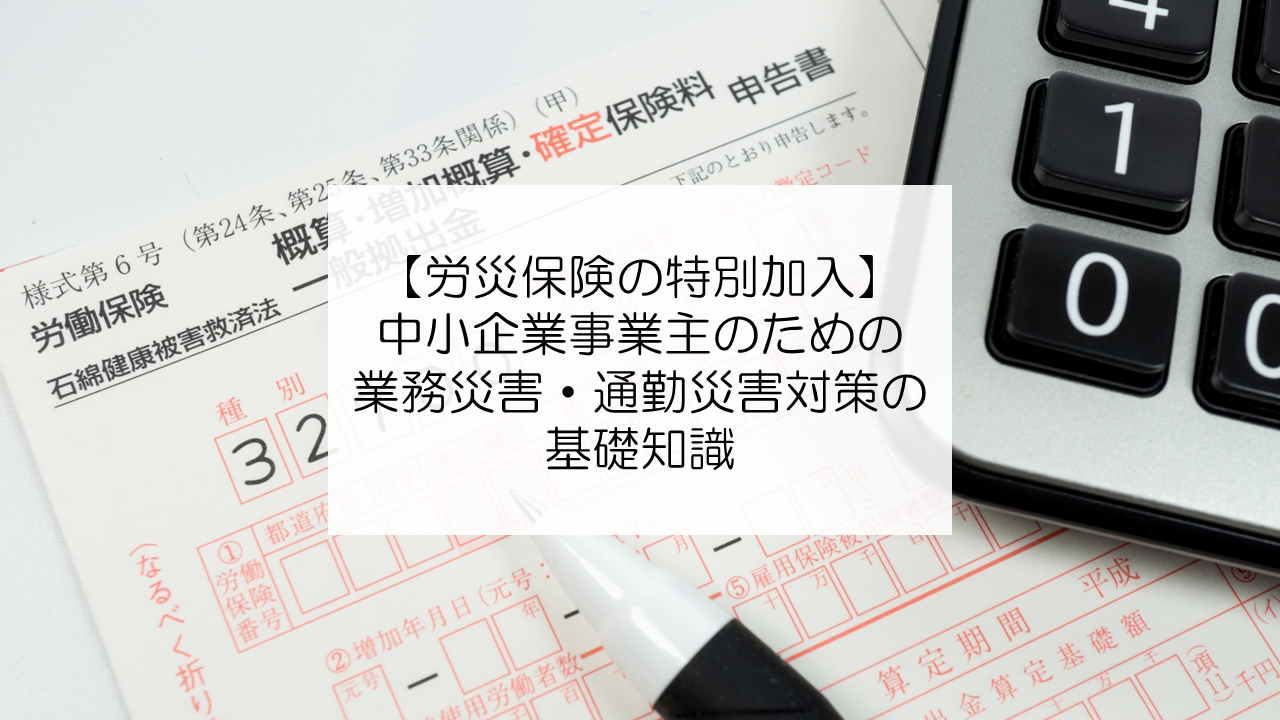
中小企業を経営していると、社員の安全管理やリスク対策に頭を悩ませることも多いかと思います。なかでも「労働者災害補償保険(労災保険)」は、業務中や通勤中のケガや病気に対して補償を行う、公的な保険制度としてよく知られています。
しかし、労災保険は「事業主自身は労災保険の対象外」であるという点には注意が必要です。特に自らも労働者と同様に現場で働く機会の多い中小企業の経営者にとっては大きなリスクになり得ます。
そこで活用したいのが、「特別加入制度」です。この制度を利用すれば、事業主や一人親方など、原則的に労災保険の対象外だった人も、一定の条件を満たせば補償を受けられるようになります。
本記事では、「中小企業の事業主のための労災保険の特別加入制度」について、基礎知識から手続き、メリット・デメリットまでわかりやすく解説します。
労災保険の特別加入制度とは?
労災保険は、原則として社員(労働者)を対象とした制度であり、事業主自身は補償の対象外です。しかし、業務に携わるリスクは事業主も変わりません。そこで用意されているのが「特別加入制度」です。
一般的な労災保険との違い
労災保険は、原則として雇用されている労働者を対象とした保険制度です。業務中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡などに対して、治療費や休業補償などの給付が行われます。
一方、特別加入制度は、本来労災保険の対象外である事業主や自営業者、一人親方、家族従業者などが、一定の条件下で労災保険に加入できる仕組みです。
これは、現場で実務に携わる立場にある事業主なども、労働者と同様のリスクを抱えているという事情を踏まえた制度で、業務災害に対する公的な備えが必要になる場合があるからです。
どのような人が特別加入できるのか
特別加入の対象者は、以下のような方々です。
- 中小企業の事業主(一定の要件あり)
- 一人親方(建設業などで自分一人で業務を行う人)
- 家族従事者(労働者として雇用契約はないが実際に業務に従事している家族)
- 自営業者(農業、林業、漁業等の個人経営者)
- 海外派遣者 など
中小企業の事業主が特別加入制度を活用するためには、労働保険事務組合を通じて加入手続きを行う必要があります。
中小企業事業主が特別加入できる条件とは
中小企業事業主が特別加入をする場合には、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。また、労働保険事務を委託するためには、事業規模の要件があります。
特別加入が認められる事業主の範囲
中小企業の事業主が特別加入できるのは、労働保険事務組合に事務委託している場合にかぎられており、また、業種ごとに労働者数の上限が定められています。
- 小売業:常時50人以下
- サービス業:常時100人以下
- その他の業種(製造業など):常時300人以下
この範囲内で、事業主自身が業務に従事している場合、特別加入の対象とされます。
実際の加入手続きと必要書類
加入手続きの主な流れは以下の通りです。
- 労働保険事務組合を通じて申し込み
- 必要書類の提出(申請書、健康診断書など)
- 加入承認後、労災保険料の納付
中小企業事業主にとっての特別加入のメリット・デメリット
特別加入を行う最大のメリットは、中小企業事業主や役員も業務災害・通勤災害に対する補償を受けられるようになることです。補償内容は労働者とほぼ同等のものとなります。
補償の内容と給付の具体例
特別加入をすると、事業主自身も以下のような労災保険の給付を受けられます。
- 療養補償給付(治療費全額)
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 介護補償給付
- 葬祭料
たとえば、機械作業中に負傷したり、通勤途中に交通事故に遭ったりした場合などでも補償を受けられます。
費用負担と他の保険とのバランス
特別加入をするためには労働者に対する労災保険料の他に費用負担が発生します。保険料は、給付基礎日額(3,500円~25,000円)と、業種に応じた保険率で決まります。業種によっては保険料が高くなることもあります。
また、民間の傷害保険や所得補償保険と補償内容が重複する場合もあるため、全体の保険設計とのバランスを見て検討することが大切です。
特別加入を検討する上での注意点
特別加入は、中小企業事業主や役員等も労災保険の補償を受けることができる、という点においてはメリットが大きいですが全ての中小企業にお勧めできるものではありません。
特別加入をした場合、特有の手続きが発生したり手続き上の管理が必要になったりする場合もあります。
特別加入をした場合に発生する事務手続き等
特別加入をした場合に発生する事務手続き等は、以下のようなものがあります。
- 労働保険年度更新を労働保険事務組合に対して行うこと
- 特別加入者の業務内容に変更があった場合の届出
- 給付基礎日額の変更手続き
特別加入をすることでメリットを得られるケース
特別加入をすることでメリットを得られる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 家族経営などで事業規模が比較的小さい場合
- 事業主や役員自らが現場作業にあたることが多い場合
- 事業主や役員が危険を伴う業務に従事する場合
特別加入のメリットを得られないケース
事業主や役員が現場に入らず、経営者としての業務にあたっている場合は、特別加入をしていたとしても労災保険の補償の対象外となります。
そのため、経営者としての業務に専念できるのであれば特別加入をする必要はありません。
労災保険の特別加入と民間の損害保険の比較
労災保険の特別加入との比較対象となるのが民間の損害保険です。どちらかい一方を選択することもあれば併用するケースもあります。
保険料の比較
国が運営している労災保険の特別加入の方が低い保険料で長期的な補償を受けられる可能性があります。特に業務災害などによる怪我の療養が長期間になるほど特別加入の方が大きなメリットを得られることが考えられます。
補償内容の比較
補償内容は、特別加入は労働者に対する補償内容とほぼ同等ですがどのような業務中に補償を受けられるかには一部制限があります。また、交通事故などによって相手方に損害を与えた場合の補償は対象外です。
一方で、民間の損害保険であれば自らの休業損害の他にも相手方の補償に備えることもできるでしょう。
手続き方法の比較
保険加入から補償を受ける段階まで民間の損害保険の方が手続きは簡単です。例え、難しい手続きであっても損害保険の営業担当者のサポートを受けられるでしょう。
一方で、特別加入に関しては、通常の労災保険と同等、あるいはそれ以上の手続き負担が生じることがあります。労働保険事務組合や社会保険労務士のサポートを受けたとしても事務手続きの負担は小さくありません。
まとめ
労災保険の特別加入制度は、中小企業の事業主にとって、自らの身を守るための大切な制度です。補償内容を理解し、必要な手続きをしっかりと行えば、公的制度を活用したリスク管理が可能になります。
しかし、特別加入は手続きがやや複雑で、条件や必要書類、保険料の選定など、事業主ごとに検討すべき点が異なります。自社にとって本当に必要かどうかを判断するためにも専門家に相談することをおすすめします。