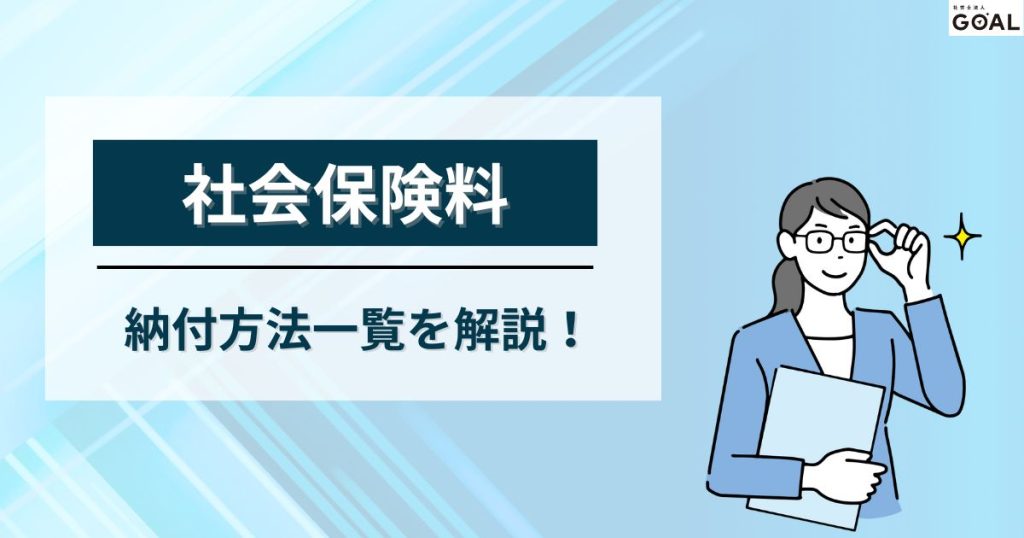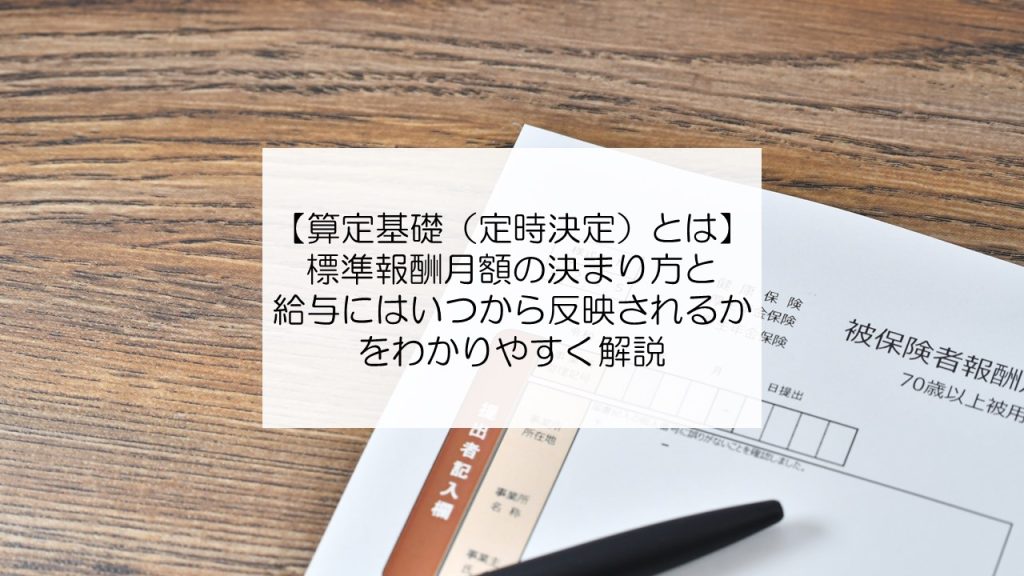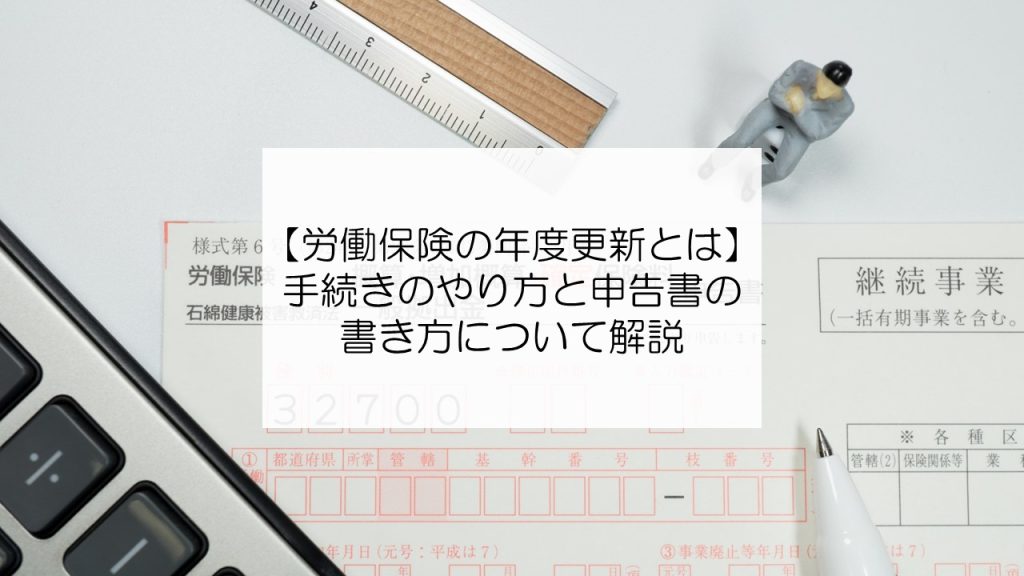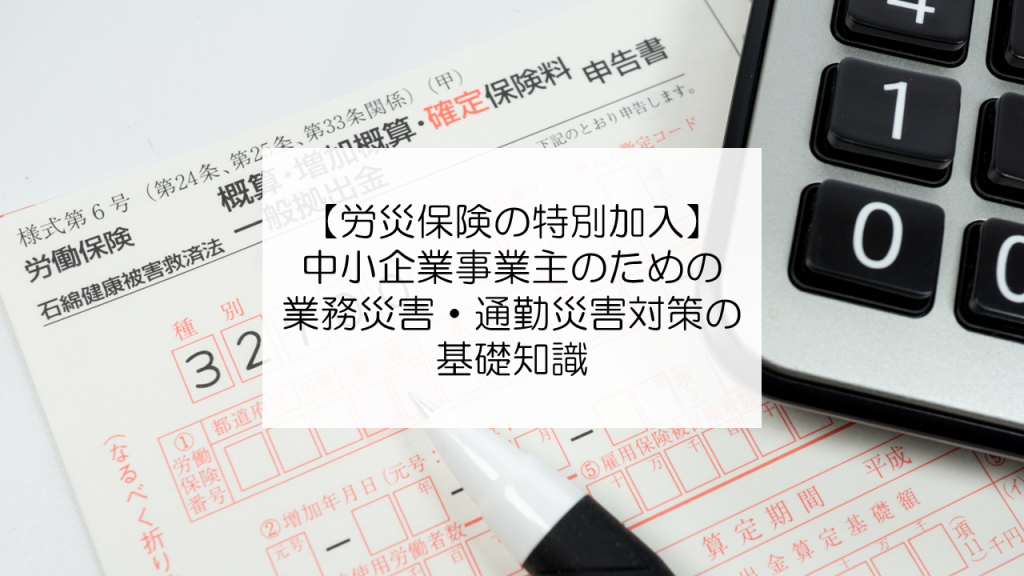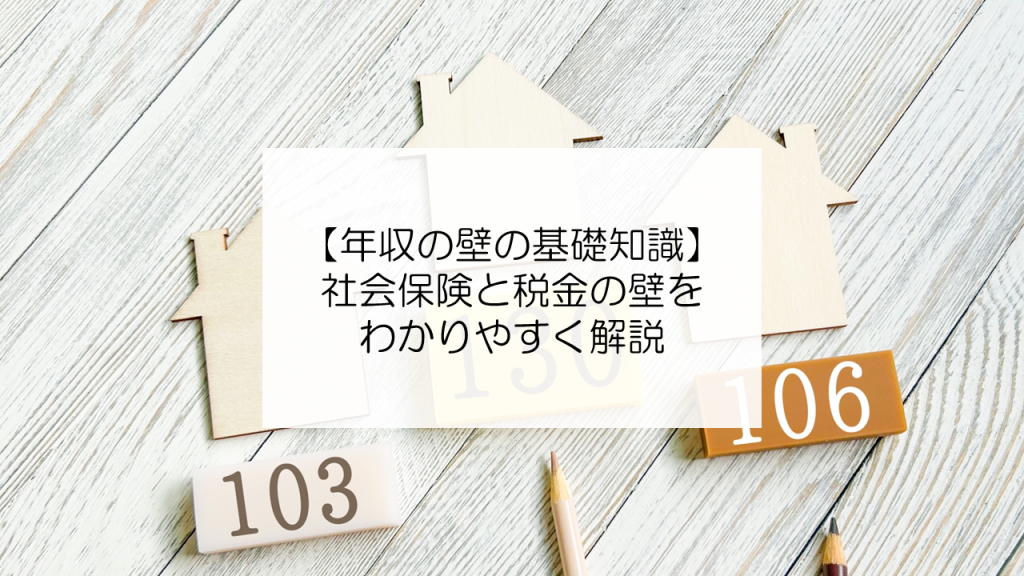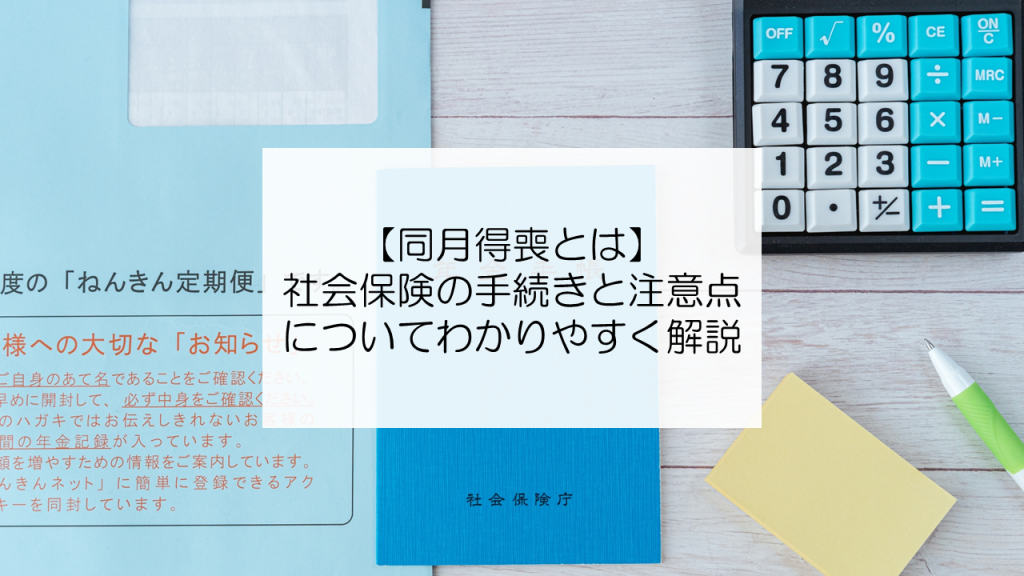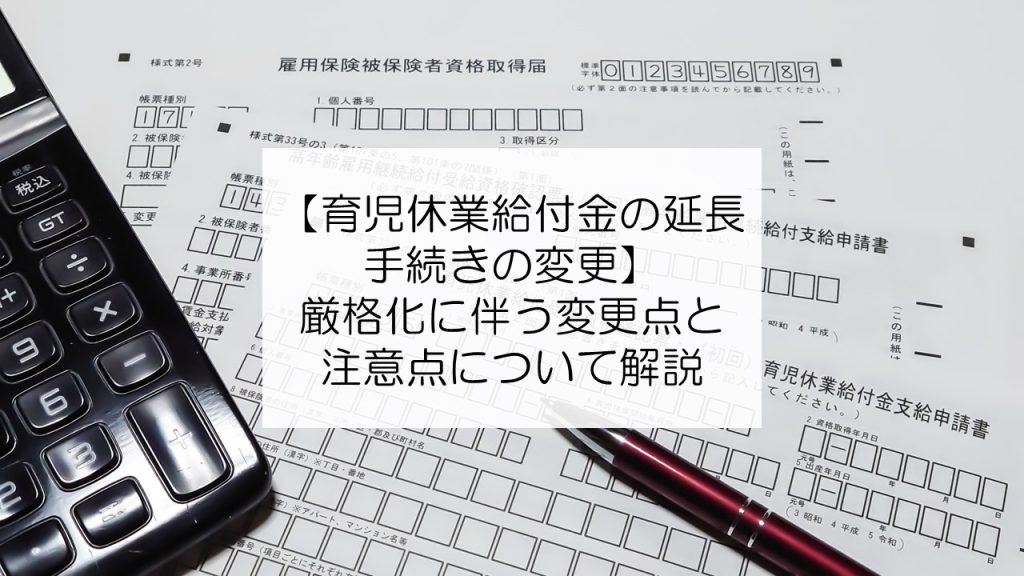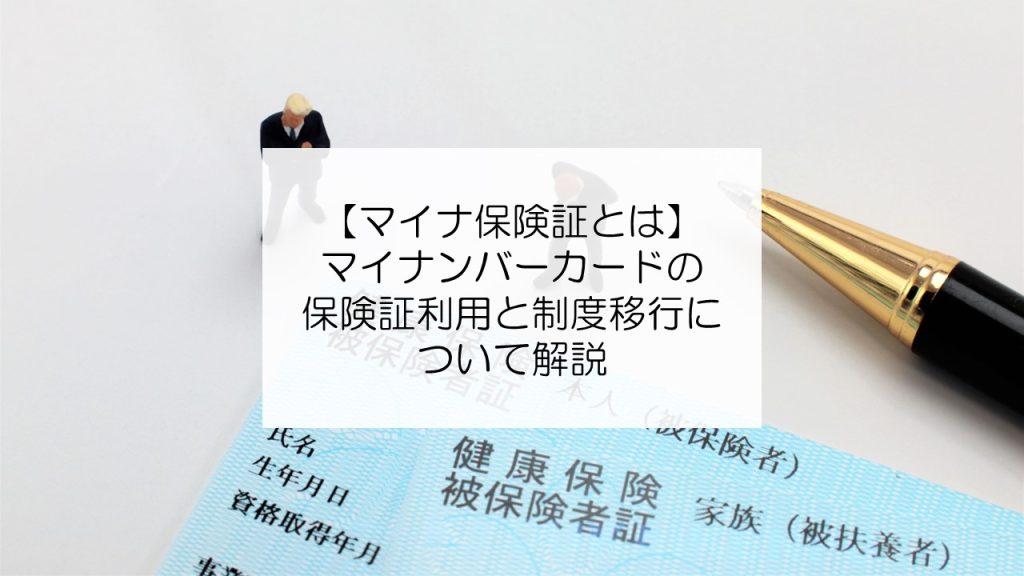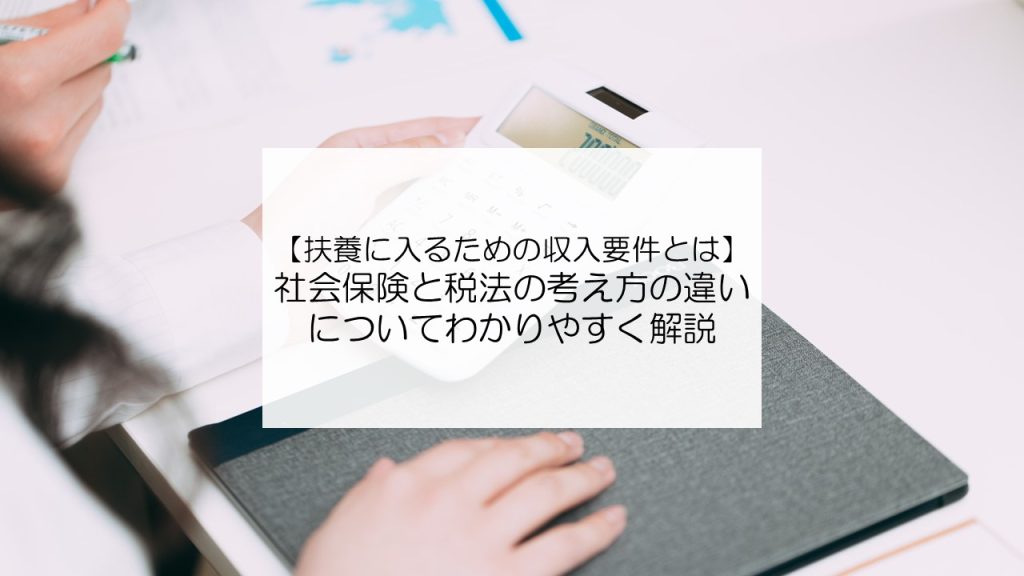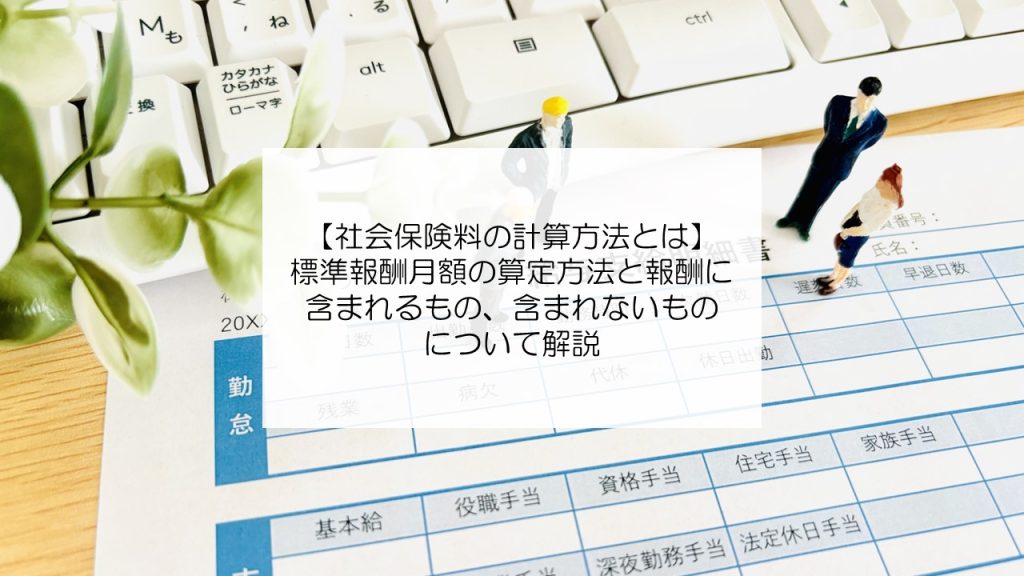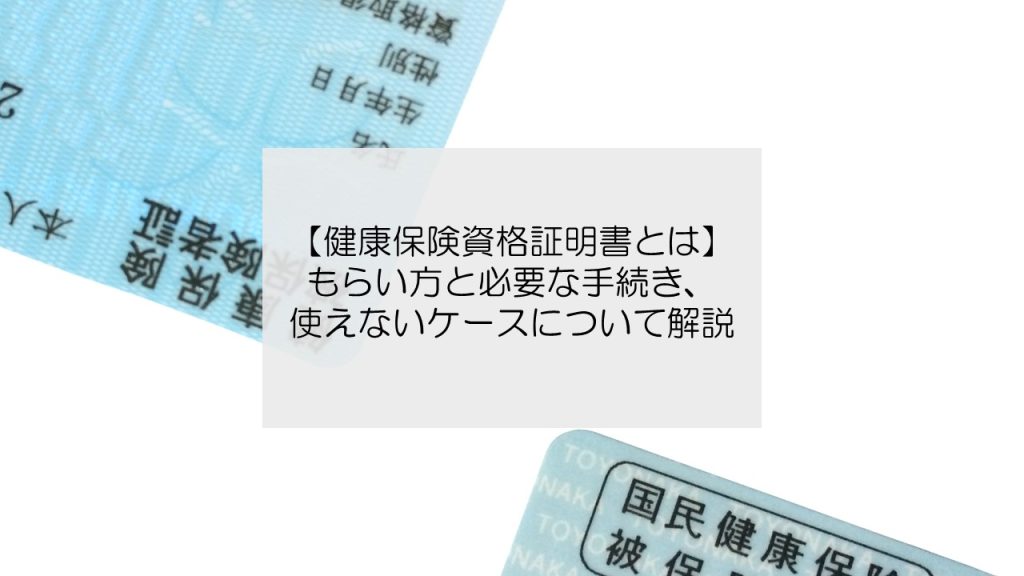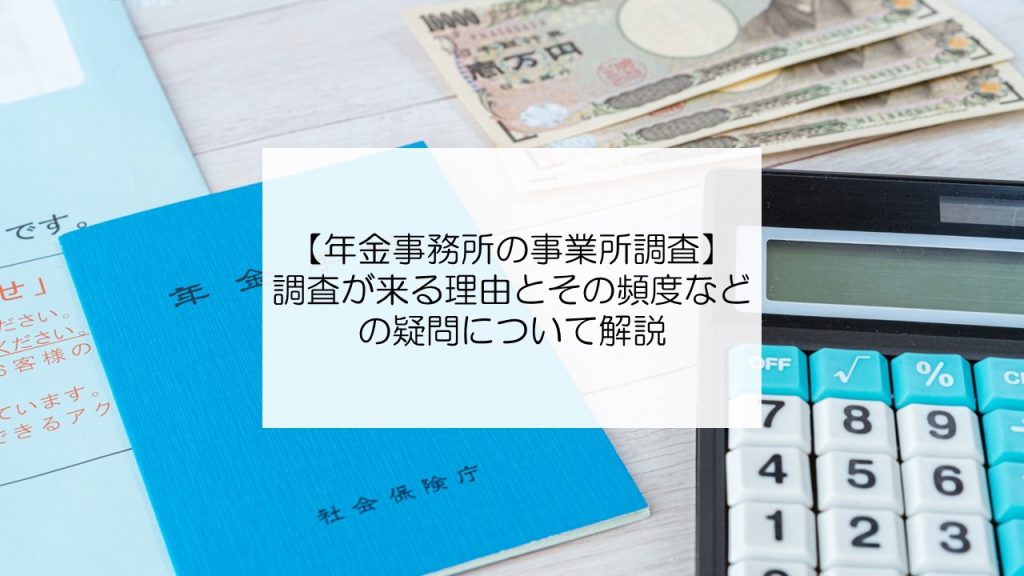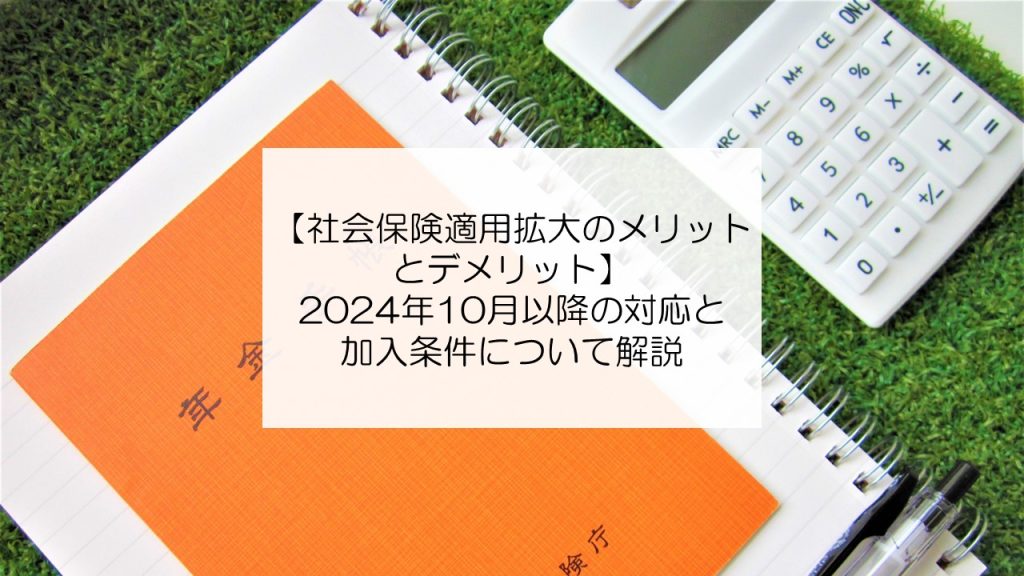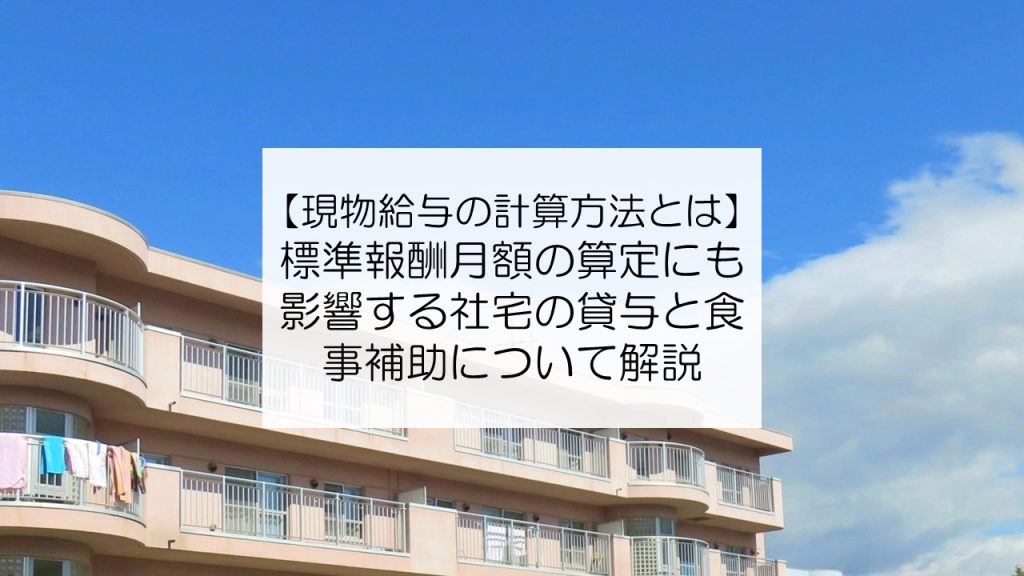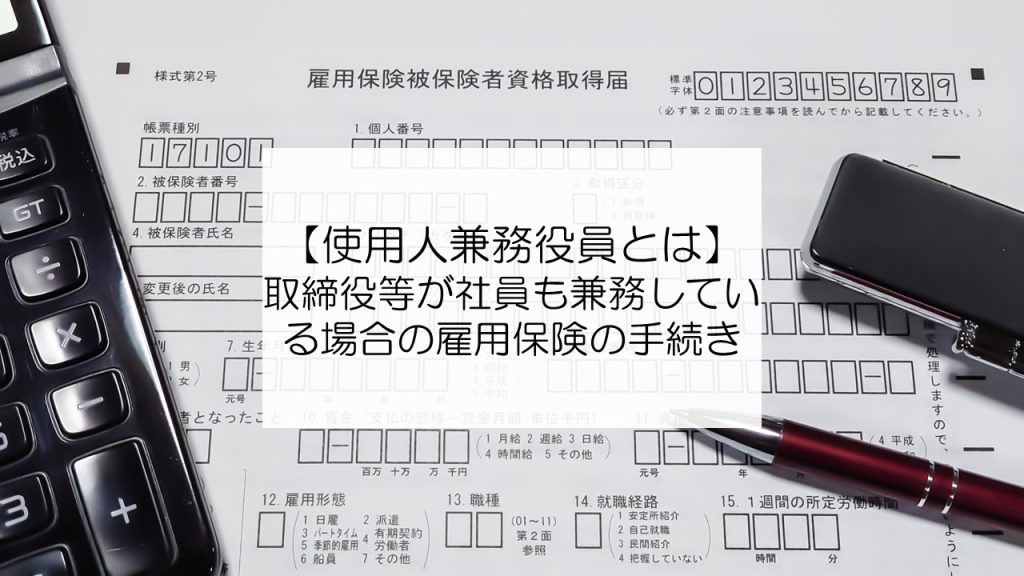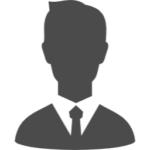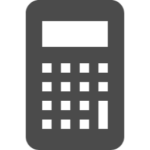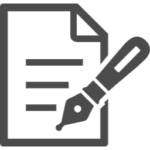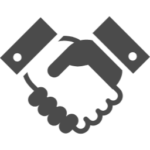社会保険・労働保険– category –
-

社会保険料の納付方法は?法人のクレジットカード払いについて
法人は、従業員を雇うと、従業員の給与や賞与から健康保険と厚生年金保険の社会保険料を毎月差し引き、事業主負担分と合わせて期限までに納付しなければなりません。 パートやアルバイトの従業員に対する社会保険の適用範囲が拡大しつつある中、保険料の増... -

算定基礎(定時決定)とは?標準報酬月額の決まり方と給与にはいつから反映されるかをわかりやすく解説
算定基礎とは、毎年4月から6月の間に支払われた給与額(報酬額)をもとに、社会保険料を見直すための手続きです。 この給与額をもとに、7月10日までに(土日祝日の関係で前後することあり)日本年金機構(年金事務所)へ「算定基礎届」を提出します。 算定... -

【労働保険の年度更新とは】手続きのやり方と申告書の書き方について解説
労災保険の年度更新とは、社員に支払った給与(賃金)を元に算出した労働保険料を申告・納付を行う手続きです。 労働保険の年度更新により、前年度に概算納付していた労働保険料を確定させて過不足を清算し、同時に今年度分の労働保険料の概算額を算出して... -

【労災保険の特別加入】中小企業事業主のための業務災害・通勤災害対策の基礎知識
中小企業を経営していると、社員の安全管理やリスク対策に頭を悩ませることも多いかと思います。なかでも「労働者災害補償保険(労災保険)」は、業務中や通勤中のケガや病気に対して補償を行う、公的な保険制度としてよく知られています。 しかし、労災保... -

【年収の壁の基礎知識】社会保険と税金の壁をわかりやすく解説
パートタイマーやアルバイトで働く人、あるいは配偶者の扶養に入って働いている人にとって、気になるキーワードで「年収の壁」という言葉があります。 一見すると「少しぐらい年収が上がっても問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、年収が一定のライ... -

社会保険の同月得喪とは?注意点についてわかりやすく解説
「同月得喪(どうげつとくそう)」とは、同じ月の中で社会保険の資格を取得(得)し、同じ月内に喪失(喪)することを指します。 例えば、ある社員が月の初めに入社し、その月のうちに退職した場合、同月得喪の扱いとなる可能性があります。 この仕組みを... -

育児休業給付金の延長とは?保育所入所保留通知書と制度変更の注意点【社労士が解説】
育児休業給付金は、育児休業を取得する雇用保険被保険者である社員に対し、収入減少を補うための支援制度です。この育児休業給付金について、2025年4月から支給対象期間延長手続きが厳格化されることになりました。 育児休業給付金の延長手続きの厳格化は... -

【マイナ保険証とは】マイナンバーカードの保険証利用と制度移行について解説
2024年12月、これまで利用されてきた健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が本格的に始まります。これに伴い、中小企業の事業主や総務担当者は、社員への適切な案内やサポートが重要になります。 ... -

【扶養に入るための収入要件とは】社会保険と税法の考え方の違いについてわかりやすく解説
扶養の考え方は、社会保険と税法とで異なります。パートタイマーやアルバイトを採用したとき「扶養の範囲内で働きたい」といわれるケースがありますが、それがどちらの扶養のことを指しているかにより満たすべき条件が違います。 今回は、いわゆる「扶養に... -

【社会保険料の計算方法とは】標準報酬月額の算定方法と報酬に含まれるもの、含まれないものについて解説
社会保険料を計算するには、標準報酬月額を算定する必要があります。標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために社員の月々の給料を等級に区分した金額のことです。 標準報酬月額を算定するには、「報酬」に含まれるもの含まれないもの、標準報酬月額の... -

【健康保険資格証明書とは】もらい方と必要な手続き、使えないケースについて解説
健康保険資格証明書は、社員が新たに入社したときなどに健康保険証が手元に届くまでの間に病院へ行く必要があるような場合に手続き中であることを証明し、保険診療を受けられるようにするためのものです。 この健康保険資格証明書について「健康保険証と同... -

【年金事務所の事業所調査】調査が来る理由とその頻度などの疑問について解説
日本年金機構(年金事務所)は、事業主に対して社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きが適切に行われているかを確認するために定期的、あるいは随時必要なタイミングで事業所調査を実施しています。 法人の事業所及び常時5人以上の従業員が働く個人事... -

【社会保険適用拡大のメリットとデメリット】2024年10月以降の対応と加入条件について解説
社会保険適用拡大は、2016年10月以降、従業員数501人以上の企業を対象にスタートし、2022年10月1日からは101人以上の企業まで適用拡大されてきました。さらに2024年10月1日からは51人以上の企業も対象になるため多くの中小企業に影響することが予想されま... -

【現物給与の計算方法とは】標準報酬月額の算定にも影響する社宅の貸与と食事補助について解説
会社が社員に社宅を貸与したり食事を支給したりする場合、それらは現物給与として扱われ社会保険料の算定対象に含まれることがあります。 現物給与として支給したものを社会保険料の算定対象に含まずに標準報酬月額を決定してしまうと社会保険料が不当に低... -

【使用人兼務役員とは】取締役等が社員も兼務している場合の雇用保険の手続き
使用人兼務役員とは、法人の役員と社員としての立場を両方とも有しているような人のことを言います。 普通、取締役等の会社役員は雇用保険には加入できません。しかし、使用人兼務役員に認定されると雇用保険被保険者として資格を取得することができます。...
12