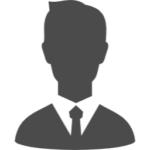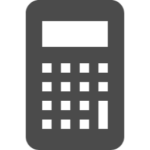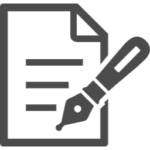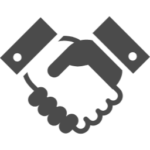賞与・ボーナスの金額の決め方と基本ルール

企業において「賞与(ボーナス)」は、社員のモチベーション向上や定着率の向上に寄与する重要な報酬制度の一つです。しかし、その金額の決め方や支給ルールについて、明確な基準を設けていない企業も多く、支給のたびに「どの程度支給すればよいのか」「支給金額はどのように決めればよいのか」と悩む経営者や人事担当者も少なくありません。
特に昨今では、インフレや最低賃金の上昇、働き方改革の影響もあり、給与体系の見直しが進む中で「賞与の支給ルールを整備したい」というご相談が増えています。また、就業規則に明記していない賞与制度が、従業員とのトラブルの原因になるケースも見受けられます。
本記事では、「賞与・ボーナスの金額の決め方とルール」について、法律的な根拠や実務的な設計方法を交えながらわかりやすく解説していきます。
賞与・ボーナスの基本とは?その目的と法的な位置づけ
賞与(ボーナス)は、企業が従業員に対して支給する給与以外の報酬であり、一般的には企業の業績や個人の評価に応じて支給されるものです。しかし、賞与の支給は法律上の義務ではなく、あくまで任意の制度であることをまず理解しておく必要があります。
賞与と給与の違いとは?
賞与と給与の大きな違いは「支給の義務」と「支給の頻度」にあります。給与は労働の対価として月に一度等の一定期間毎に支払う義務がある一方で、賞与は企業の判断で支給の有無や金額が決まるものです。そのため、賞与はあくまで「特別な報酬」「臨時的な報酬」として位置付けられます。
賞与の法的ルールと就業規則への記載義務
労働基準法には賞与に関する明確な支給義務は定められていませんが、就業規則や労働契約書に支給に関する記載がある場合、それが拘束力を持つようになります。
たとえば「年2回支給」と明記されているにもかかわらず、一方的に支給を中止した場合は、労働契約違反とみなされ、トラブルにつながる恐れもあります。したがって、賞与制度を導入する際は、就業規則または賃金規程などにその支給条件や支給時期、評価方法などをできる限り明確に規定し、従業員へ周知することが必要です。
金額の決め方|公平性と納得感を両立させるポイント
賞与額は本来、企業が自由に決定することができます。しかし、経営者・事業主の主観が入りすぎてしまうと従業員間で不公平感が生まれる恐れがあります。そのようなことを防ぐためには評価制度と連動させる等、できる限りわかりやすく制度設計をすることが求められます。
評価制度と連動させた賞与設計の基本
賞与額の決定にあたっては、評価制度と連動させることが公平性・納得感を高める鍵となります。業績評価や目標達成度、行動評価などを基準にし、明確な指標で査定することで、支給額に対する従業員の理解が得られやすくなります。
定額・基本給連動・業績連動の3パターンとそのメリット・デメリット
賞与額の決定方式には大きく分けて3つのタイプがあります。
- 1. 定額支給型:支給額が一律で明確。納得性は高いが成果反映が難しい。
- 2. 基本給連動型:役職や給与に応じた調整がしやすく、実務で最も多い方式。
- 3. 業績(評価)連動型:会社の利益や個人の評価と連動しやすく、財務の健全性を保ちやすいが支給額が変動しやすい。
企業文化や財務状況に応じて、適した方式を選択することが大切です。
「揉めない賞与額設定」の考え方
賞与額の決定には、従業員間の公平性、業績反映、評価の透明性が求められます。トラブル防止の観点としては「評価基準の明文化」と「支給ルールの周知」が制度設計の要です。また、退職者や休職者、試用期間中の扱いも明確に定めることがトラブル防止に有効です。
「支給日在籍要件」は有効か
賞与の支給に際しては「支給日在籍要件」を設ける企業も少なくありません。これは、賞与支給日(例:6月30日や12月20日)に在籍していない従業員には賞与を支給しないというルールです。
このような要件は法的に無効ではありませんが、就業規則や賃金規程に明記されていない場合、後からの適用はトラブルの原因になります。また、例え就業規則や賃金規程で明文化されていたとしても「特定の(退職予定の)従業員に支給しないこと」を目的として事業主・経営者が恣意的に支給日を変更した場合には無効となるケースもあるため注意が必要です。
賞与支給の実例と注意点
賞与は任意恩恵的な制度であり、支給の有無や金額は企業が決定することができるものです。しかし、支給実績(支給時期)や金額等が一定である場合、それが企業慣習となり従業員の既得権となっている場合もあります。そうすると、突然の賞与廃止や支給時期の変更がトラブルとなることもあります。
よくあるトラブル事例と解決方法
支給基準が不明確であったり、評価と支給額の整合性が取れていなかったりすることで、従業員の不満が噴出するケースは少なくありません。社労士等の専門家の指導のもとに制度を再設計し、評価・支給の仕組みを整えることで、納得度の高い制度に改善された事例は少なくありません。
支給月や評価タイミングの注意点
賞与は一般的に、夏と冬に支給されますが、評価時期と支給時期がずれていると従業員が不満を抱きやすくなります。制度設計時には、評価→通知→支給の流れがスムーズになるよう調整することが重要です。
少なすぎる賞与は逆効果
賞与は任意恩恵的な制度であり金額設定は企業の自由である旨は既にお伝えした通りです。しかし、世間相場や業界相場よりも極端に低い金額となると人材流出やモチベーション低下の原因となってしまいます。
賞与を支給することで企業が赤字に陥ってしまっては本末転倒ですが、支給するのであれば世間一般的な支給金額や同業他社と大きく見劣りすることのないように注意してください。
賞与に関わる法律と社会保険・税金の取扱い
賞与に関わる社会保険料と税金の取り扱いは、通常の給与とは異なります。給与とのルールの違いを正しく理解して適切な計算を行うようにしましょう。
賞与にかかる社会保険料・雇用保険料の計算方法
賞与は社会保険料・雇用保険料の対象です。社会保険については支給月ごとに「賞与支払届」を提出し、標準賞与額(上限あり)に基づいて保険料を算出します。雇用保険に関しては支給の都度の届け出はありませんが労働保険料の算定の際には、賞与を含めて計算を行います。
源泉徴収の注意点と企業側の義務
賞与は、支給時に源泉徴収が必要です。給与所得の源泉徴収税額表を基に、前月給与をもとにした計算を行います。給与計算時の源泉所得税の計算方法とは異なるので計算ミスのないようにしましょう。
まとめ
賞与制度は企業の信頼と成長を支える重要な仕組みです。明確な基準と公正な運用があれば、従業員の定着率やモチベーション向上に寄与します。その一方で、制度設計の失敗により従業員に不信感を抱かせてしまう恐れもあります。
任意恩恵的な制度として正しく運用するために事前の制度設計をしっかりと行うようにしましょう。