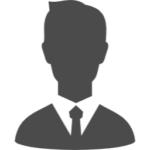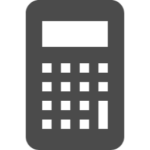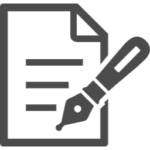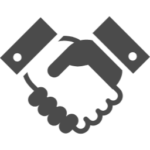社会保険の同月得喪とは?注意点についてわかりやすく解説
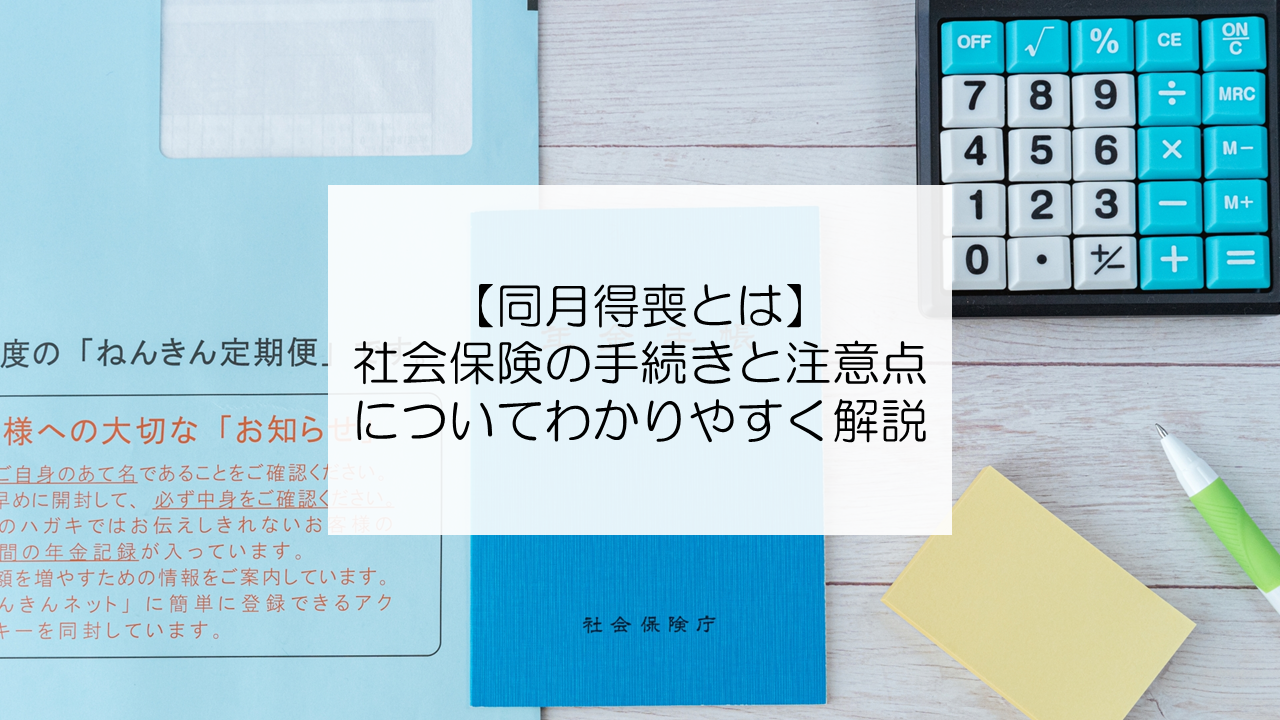
「同月得喪(どうげつとくそう)」とは、同じ月の中で社会保険の資格を取得(得)し、同じ月内に喪失(喪)することを指します。
例えば、ある社員が月の初めに入社し、その月のうちに退職した場合、同月得喪の扱いとなる可能性があります。
この仕組みを正しく理解しておかないと、社会保険料の計算を正しく行うことができず、退職した社員へ社会保険料を還付したり、逆に追加で徴収しなければいけなくなったりと無駄な事務負担が発生してしまうことがあります。
本記事では、同月得喪の基本ルールや適用条件、手続きの流れなどについて解説します。全体の社会保険手続きの流れを押さえた上で、同月得喪についても理解していきましょう。
同月得喪の基本ルールと適用条件
「同月得喪(どうげつとくそう)」とは、同じ月の中で社会保険の被保険者資格を取得(得)し、同じ月内に喪失(喪)することを言います。
通常、社会保険は資格を取得した月から保険料が発生し、資格を喪失した月の前月まで保険料がかかります。しかし、同月内に取得と喪失が発生すると通常の取り扱いとは異なる対応が必要になります。
同月得喪の具体例
同月得喪が発生するケース、同月得喪とはならないケースは次の通りです。
入社後すぐに退職した場合
例えば、ある社員が4月1日に入社し、4月25日に退職したとします。この場合、4月1日に社会保険に加入(資格取得)し、4月25日に退職と同時に社会保険を喪失(資格喪失)します。同じ4月内に資格取得と喪失が発生するため、同月得喪になります。
月末退職の場合は同月得喪にはならない
同じように4月1日に入社した場合でも4月30日(月末)に退職した場合には、同月得喪にはなりません。この場合、社会保険の資格喪失日は5月1日(退職日の翌日)となるため、同月得喪とはなりません。
同月得喪が発生した場合の社会保険料の計算方法
同月得喪が発生するとその月は、健康保険料のみ発生することとなり厚生年金保険料は発生しません。
通常の社会保険料の仕組み
社会保険料は、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した日の属する月の前月分まで発生します。
また、社会保険料は「翌月徴収」が原則ですから、4月1日に入社した社員の社会保険料は5月支払い分の給与から控除することになります。
同月得喪の場合の厚生年金保険料
厚生年金保険料は、保険料の二重払いを防ぐ観点から同月得喪により資格喪失をした同月内に他の年金制度の資格取得手続きを行うことで会社に還付されます。
退職をした元社員本人が国民年金保険等への資格変更の手続きをした場合、会社に対して厚生年金保険料(事業主負担分と社員負担分の両方)が還付されます。
同月得喪の場合の健康保険料
健康保険料は、同月内に転職して新たに健康保険被保険者資格を取得したときも再就職せずに国民健康保険等へ資格が変更された場合も還付される仕組みはありません。
雇用保険料は同月得喪の場合でも発生する
雇用保険の資格取得・喪失は同月得喪の場合でも発生した賃金に対して保険料が発生するため通常どおり控除します。
同月得喪の手続き
同月得喪が発生する場合、手続きの流れや制度についての理解が足りないと社会保険料の徴収ミスが起こり得ます。ここでは、企業側の具体的な手続きの流れを解説します。
社会保険資格取得届の提出
社員が入社した時点で「健康保険・厚生年金保険資格取得届」を提出します。
社会保険資格喪失届の提出
同月内で退職することになった場合でも通常通り「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
給与の日割り計算と社会保険料の徴収
給与は賃金規程に基づいて日割り計算を実施します。社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)については、1箇月分の保険料を通常通り徴収しておくとよいでしょう。
雇用保険料と源泉所得税については、支払額に応じて計算した金額を徴収します。
事業主宛に「還付請求書」が届く
退職した社員(元社員)が同月内に再就職をして社会保険被保険者資格を取得したり、国民年金への資格変更をしたりした後、事業主宛に「還付請求書」が届きます。会社はそれをもって還付請求を実施します。
厚生年金保険料が還付された後、元社員へ保険料を返金する
会社宛に厚生年金保険料が還付された後に元社員に対して本人負担分の返金をするとよいでしょう。
同月得喪の注意点
「同月得喪の手続き」でお伝えした①から⑤までの手順にはいくつかのポイントがあります。ここでは、そのポイントを踏まえた注意点を示します。
同月得喪の場合でも社会保険料は控除しておく
同月得喪のときでも健康保険料は発生します。厚生年金保険料の本人負担分は後から還付されますが、退職した社員がいつまでも再就職や国民年金への資格変更を行わなかった場合、本人負担分の回収に遅れが生じてしまいます。
退職した社員との連絡手段の確保
同月得喪のようなケースでは、入社して間もなく突然来なくなってしまうようなことも珍しくありません。
数日間しか働いていないような場合、日割り計算した給与より社会保険料の方が多くなってしまうこともあります。そうすると社員に社会保険料分の入金を依頼しなくてはならないこともあるでしょう。
企業としては、日ごろからこのようなケースも想定して社員との連絡手段を考えておくようにしてください。
まとめ
本記事では、同月得喪の基本ルールや適用条件、手続きの流れなどについて解説してきました。
同月得喪は、同じ月内で社会保険の資格取得と喪失が発生する場合に適用され、社会保険料の発生の仕組みが通常とは異なることに注意が必要です。
給与計算や社会保険関係の手続き事務を行う担当者としては、この仕組みを正しく理解しておかないと無駄な事務負担が発生してしまいます。