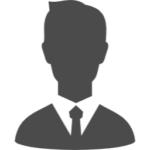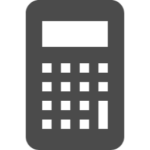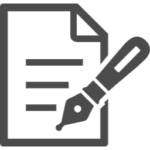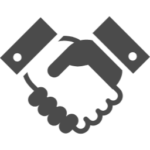【年収の壁の基礎知識】社会保険と税金の壁をわかりやすく解説
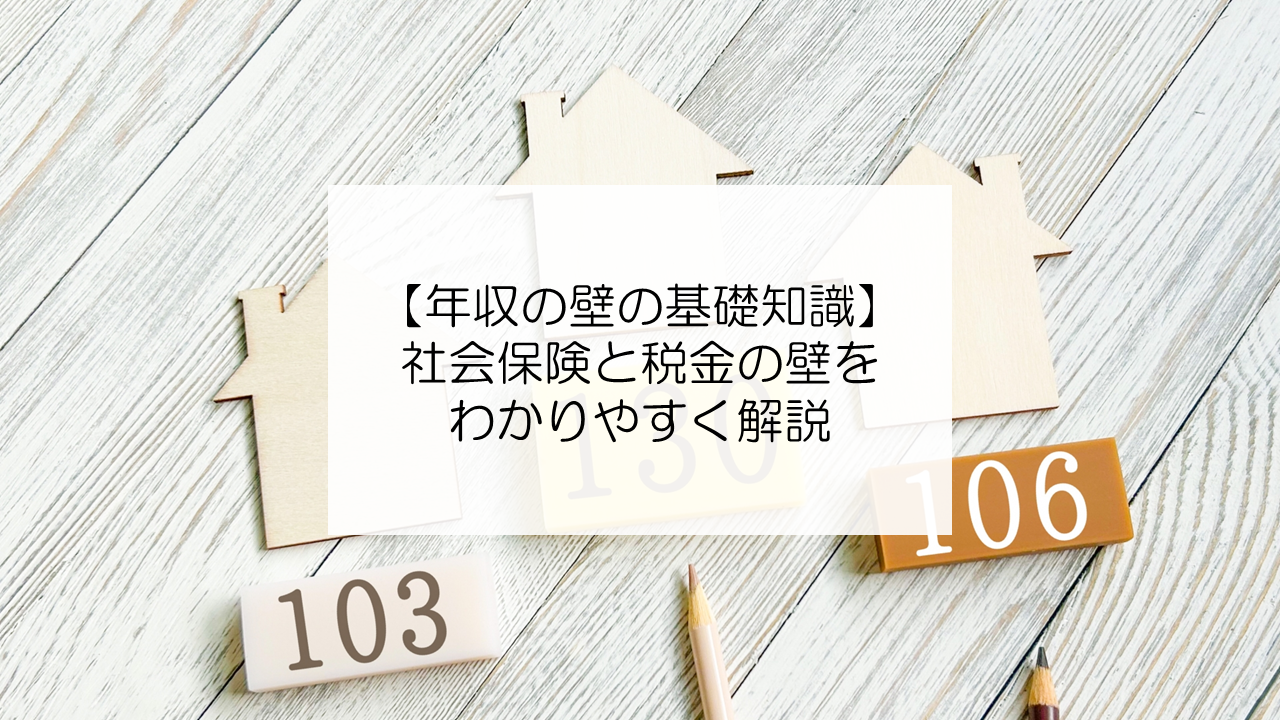
パートタイマーやアルバイトで働く人、あるいは配偶者の扶養に入って働いている人にとって、気になるキーワードで「年収の壁」という言葉があります。
一見すると「少しぐらい年収が上がっても問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、年収が一定のラインを超えると、社会保険料の負担が発生したり、税金上の優遇が受けられなくなったりすることがあります。
この“見えないボーダー”を意識せずに働き方を決めてしまうと、「せっかく働いたのに手取りが減ってしまった」といった事態にもなりかねません。また、多くの人が気にしているにもかかわらず、内容を正しく理解できていないのが現状です。
この記事では、社会保険と税金における「年収の壁」について整理して解説していきます。
社会保険の「年収の壁」とは
社会保険の年収の壁には「年収106万円」と「年収130万円」の2つの壁が存在します。
106万円の壁は勤務先の規模で変わる
「106万円の壁」は、特定の条件を満たすパート・アルバイトに適用される厚生年金保険・健康保険の加入ラインです。
特定適用事業所に勤めている場合で、以下のすべてに該当する人の年収が106万円(月収換算で約8.8万円)を超えると、社会保険への加入が義務付けられます。
- 勤務先の従業員数が51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生ではない
社会保険に加入すると保険料が発生しますが、同時に厚生年金保険を受給できたり健康保険の給付が受けられたりというメリットもあるため、単純に「損」とも言い切れません。
「特定適用事業所」とは
「特定適用事業所」とは、従業員数が一定数人以上の企業で、パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者であっても一定の条件を満たせば、厚生年金や健康保険への加入義務が発生する事業所のことを指します。
ここでいう従業員数は厚生年金保険被保険者数を意味し、2024年10月からは51人以上に拡大されました。
つまり、「自分の会社が特定適用事業所かどうか」で、106万円を超えたときの社会保険加入義務があるかないかが変わるのです。
130万円の壁とは
配偶者の扶養内で働いている人が意識すべきラインが「130万円の壁」です。
年収が130万円未満であれば、配偶者の扶養に入り、自身で社会保険料を支払わなくてもよいというメリットがあります。
逆に年収が130万円以上になると、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入する必要があり、手取りが大きく減少するケースもあります。
また、勤務先で社会保険に加入できる場合は、自分で厚生年金・健康保険に加入することになります。
特定適用事業所以外で働くパートタイマーの社会保険加入条件
特定適用事業所以外、つまり従業員数が50人以下の事業所では、一定の条件に当てはまる短時間就労者(パートタイマー・アルバイトなど)が社会保険に加入する義務が発生します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 事業所と常用的使用関係にあること
- 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員比較して4分の3以上であること
このような条件に該当する場合、たとえ勤務先の規模が小さくても、厚生年金保険や健康保険への加入義務が発生します。
社会保険「年収の壁」突破前のチェックリスト
社会保険の年収の壁を越えるかどうかの判断をする際には、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 扶養から外れることでどのくらい保険料が発生するか
- 社会保険に加入した場合、将来的な年金受給額はどう変わるか
- 収入の見込みが継続的かどうか
- 家計全体で見た手取りはどうなるか
これらを総合的に判断して、短期的な「手取り減」にとらわれず、将来の保障や世帯全体の収支バランスを考えることが大切です。
税金における「年収の壁」
税金について考える年収の壁は主に「100万円・103万円・150万円・201万円」の4つです。これらは、納税者本人の所得などによって対象者が変わります。
100万円・103万円の壁:所得税・住民税の扶養控除ライン
税金面での最初の壁が100万円と103万円です。
100万円の壁:
多くの自治体で、年収が100万円を超えると住民税が課税されます。
103万円の壁:
年収が103万円を超えると、所得税が課税され始めます。また、配偶者が「配偶者控除」を受けられる上限でもあります。103万円以下に抑えておくことで、本人の税負担がなく、かつ配偶者の税負担も軽減されるという点で、多くの方が意識するラインです。
150万円の壁:
納税者の配偶者に該当する場合、年収が103万円を超えても、すぐにすべての控除がなくなるわけではありません。150万円までであれば、「配偶者特別控除」の対象となり段階的な優遇が受けられます。
ただし、配偶者の年収などによって条件が変わるため、個別具体的に確認する必要があります。
201万円の壁:
年収が201万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になります。
ここまで来ると、配偶者にかかる税制上のメリットは完全に消失するため、扶養という概念からは実質的に外れることになります。
年収の壁と働き方
年収の壁を考えることは自身の働き方を考えることにもなります。年収の壁を超えて働くことは、一時的に収入を下げることになったとしても生涯収入は増えることとなり多くの経験を積み、スキルを身に着けることができるでしょう。
「壁内で抑える」or「壁を超えてしっかり稼ぐ」
年収の壁を意識する働き方には、「壁内で抑える」のか「壁を超えてしっかり稼ぐ」のかという大きく2つの選択肢があります。
前者は短期的に手取りが安定する一方、将来の年金額や保障が手薄になりがちです。後者は負担が増えるものの、厚生年金保険などの各種保障が充実するという長所があります。
目の前の手取り金額だけではなく長期的視点で考える
重要なのは目の前の「年収」や「手取り金額」だけではなく、年収の壁を超えることによって得られる長期的な視点を持つことができるか、です。
年収の壁を超えないようにして働くことは社会保険料や税金の負担は抑えられる一方、自身の収入や各種保障も低くなります。扶養者(配偶者)に生計を維持されており、将来的にもそのままであれば世帯全体としてのメリットは得られる可能性はあります。
逆に年収の壁を超えて働けばその分、自身の収入は増えていきます。収入と働く時間の増加によって経験やスキルを得られたり、責任ある仕事を任せられたりということが考えられます。
自身にとって優先するべきことがなにかによって働き方も変わるでしょう。
まとめ
「年収の壁」は、一見すると単なる収入のラインに思えるかもしれませんが、実際には社会保険や税金に大きく関わる重要な分岐点です。特に106万円・130万円といった社会保険の壁、そして103万円・150万円・201万円といった税金面での壁は、それぞれ意味や影響が異なります。
重要なのは、「損しないために収入を抑える」ことだけが正解ではないということです。社会保険に加入すれば将来の年金や医療保障が手厚くなるというメリットもあります。年収だけでなく、保険料・控除・将来の給付をトータルで比較する視点が欠かせません。
制度は年々改正される傾向もあるため、不安がある場合は早めに専門家に相談しましょう。